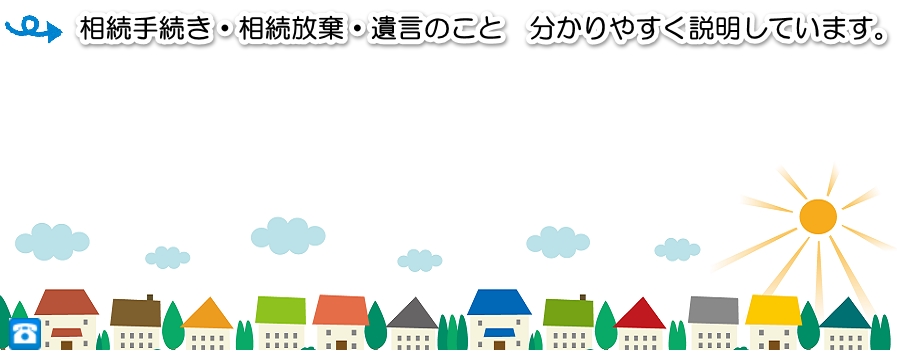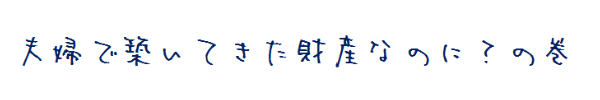
子供のいないご夫婦の一方がなくなった場合、亡くなった夫の遺産の全てを妻が相続できるでしょうか?
相続手続きの依頼を受けた際、話しをお伺いすると、当然相続できると考えられている方がいらっしゃいます。
人情的に考えれば、ご夫婦で築いてきた財産ですから、それが当たり前のように思えますが、実際の相続手続きではそうはいきません。
では、子供がいない夫婦で、夫が死亡した場合、法律上どうなっているのか、具体的に説明していきます。
ケース1(妻と亡夫の両親が相続人となる場合)
① 夫のご夫婦の両親はご健在
② 夫には、弟が一人いる
この場合の相続人は
「配偶者である妻(法定相続分3分の2)」と「夫の両親(法定相続分3分の1)」が相続人となります。
ケース2(妻と亡夫の兄弟が相続人となる場合)
① 既に、ご夫婦の両親は他界している
② 夫には、弟が一人いる
この場合の相続人は
「配偶者である妻(法定相続分4分の3)」と「夫の兄弟(法定相続分4分の1)」が相続人となります。
ケース3(妻と亡夫の姪甥が相続人となる場合)
① 既に、ご夫婦の両親は他界している
② 夫の兄弟が既に亡くなっているが、兄弟の子(甥姪)がいる。
この場合の相続人は
「配偶者である妻(法定相続分4分の3)」と「夫の兄弟の子(法定相続分4分の1)」が相続人となります。
ケース4(妻のみが相続人となる場合)
① 既に、ご夫婦の両親は他界している。
② 夫の兄弟が子がいないまま既に亡くなった。もしくは夫に兄弟がいない。
この場合の相続人は
配偶者である「妻のみ」が、相続人となります。
 このようにケース4以外の場合は、配偶者と夫の親族が相続人となるのです。
このようにケース4以外の場合は、配偶者と夫の親族が相続人となるのです。
遺言書がなかった場合の注意点
ここからは、配偶者と他の相続人が共同相続人となることにより考えられる問題について説明していきます。
相続が開始された場合(夫が亡くなった場合)
夫名義の遺産について、妻へ名義変更等の手続をする場合には、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要となり、相続人である夫の両親または兄弟姉妹の協力が欠かせません。
夫の両親や兄弟姉妹が、配偶者としての立場を理解してくれていていれば、それほど問題にはなりませんが、いざ遺産分割となった場合、そのときの兄弟姉妹の生活状況により、遺産を取得できる権利がある以上、その権利を主張する可能性もあります。
また、相続の当事者である兄弟姉妹ではなく、その兄弟姉妹の配偶者などが遺産分割について、口出しすることも考えられます。
更には、相続人全員の協力なくしては手続が進まないことを逆手にとって、法定相続分以上の主張をすることもあるかも知れません。
納得いかない場合は、家庭裁判所の調停や審判により取り決めることも可能ですが、それでも原則として、それぞれの法定相続分を基礎として話し合いがなされ、調停成立や審判までは時間がかかってしまいます。
最悪の場合(特に主要な遺産が自宅である時)
遺言による対策
まだまだ遺言の作成について、抵抗がある方も多いのですが、子供がいないご夫婦については、お互いに遺言を作成しておかれることをお勧めします。
堅苦しく考える必要はありません。「備えあれば憂いなし」です。
遺産が不動産とわずかな預貯金で兄弟姉妹が権利を主張してきた場合、兄弟姉妹の相続分を確保するためにそのわずかな預貯金を渡す、もしくは不動産を売却しなければならないという事態になってしまう可能性もあります。
このように、夫の兄弟姉妹と争いになると精神的負担も大きいでしょう。
更に、せっかく夫婦二人で頑張って築いてきた財産を分け与えなければならないとなると納得がいかないでしょう。
備えあれば憂いなし
被相続人の親が共同相続人の場合には、遺留分がありますが、兄弟姉妹の場合には遺留分はありません。
(遺留分というのは、最低限保証された相続分のことをいいます。)
遺言を残していても、この遺留分に該当する遺産については、注意・対策が必要です。
「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言を作成しておくことで、妻(配偶者)へのスムーズな相続手続きが可能となります。
なんでも準備をする、しないとでは大違い。
相続が発生した場合は、親族間で揉めることなく、スムーズに行いたいものです。その為にも事前にある程度の相続の手続きの流れと注意点を押さえておく必要があります。
ある意味これも、「相続対策」であり、最近巷で言われている「終活」とも言えるでしょう。
なかでも。自分の親族の状態や相続のトラブルを回避するための遺言について一度考えてみることは、大切です。

また、遺言書は、貴方の人生を写す、残された親族へのメッセージです。 当事務所のホームページでは、もうちょっと詳しく、相続や遺言、その他の手続きについても説明しています。興味のある方は、こちらからお入りください。
当事務所のホームページでは、もうちょっと詳しく、相続や遺言、その他の手続きについても説明しています。興味のある方は、こちらからお入りください。