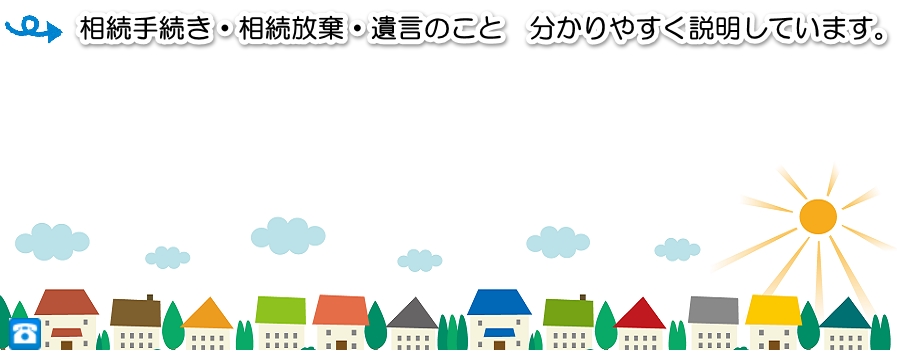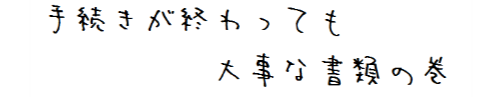
遺産相続の手続きは大変です。
預金の払い戻しや不動産の名義変更のため、相続人全員から署名やハンコ、印鑑証明書を貰ったり、銀行や法務局で手続きをすれば、これも足りない、あれも足りない・・・・
もう、何が何だか分からず目が回ります。
でも、遺産相続の手続きが終わったら、遺産分割協議書の付属書類がちゃんと揃っているか、もう一度確認してください。
全て遺産相続が終わった。と安心して、これらの書類をおろそかにすると、後々困ることがあります。
 相続人
相続人
「いずれ田舎に戻ってこようと思って、空き家のまま私が管理していたのですが、もう父が死んでから10年がたち、私も東京での暮らしに根付いてしまいました。そろそろ実家を売ろうかと思いまして・・・
司法書士
「このあたりは住宅街なので、不動産業者に依頼すれば直ぐに買い手はつくと思いますよ。」
司法書士
んっ!○○さん、この登記簿を確認してみますと自宅の前の公衆用道路の名義がお父様の名義のままですよ。先ずはこちらも相続登記の手続きをしないと売れませんね。」 相続人
相続人
「えっ、なんでだろう? 当時作った遺産分割協議書あるので見てください。」
司法書士
「○○さん、大事に保管していてよかったですね。当時の遺産分割協議書の文言で相続登記は行けますよ。ただ相続人の印鑑証明書がありません。どこに行ったのでしょう。」 相続人
相続人
「何でだろう?遺産相続のとき手続きするのに必死だったので、あまり記憶がないんです。どこかに提出したまま返してもらってないのかも・・・当時相続人だった弟はもう亡くなっているんですが、どうしたらいいでしょう?」
というわけで、どうやらこの相続人は大事な遺産分割協議の付属書類である相続人の印鑑証明書を紛失してしまったようです。
因みに、この場合は亡くなった弟の相続人全員から、当時、遺産分割協議が成立していた旨の証明を署名と印鑑証明書を添付して行ってもらう必要があります。
もし、兄と弟の相続人(兄から見て甥姪)の関係が悪かった場合はどうなるでしょう。
そうなんです。
相続登記が進まず、不動産の売買が頓挫してしまうこともあるのです。
取っておいて良かった、ご先祖様「感謝」
これとは逆に、こんなケースもありました。
敷地内にご先祖様が立てた古い蔵があり、なぜか、その蔵だけが遺産相続の登記がされていませんでした。
いざ家を新築するため住宅ローンを組もうとしたとき、通常は新築建物と一緒に、その敷地内にある蔵も担保に入れることが条件となることが多いです。
但し、その蔵の名義人が二代前のご先祖様になっているため担保に入れる手続きができません。
(亡くなっている人が契約したり、署名したりすることはできませんから、)
この場合は、ちゃんと、あるべき名義人に遺産相続の登記手続きをして、その名義人が担保に入れる手続きを行うわけです。
さて、困りました・・・ご先祖様の遺産分割協議書が出てこないと、新たに遺産分割協議書を作成しなければなりません、この場合のハンコを貰わなければならない相続人の数は15名程度、もう付き合いのない親戚も数名います。
この手続きをご説明して、必死に探して頂いたところ二代前までの遺産分割協議書が蔵に眠っていました。
遺産分割協議書の文言を確認したところ、蔵の遺産相続にも使える。
これで万事休す。
蔵の遺産相続の手続きは、他の相続人の協力なしに無事終わりました。
古い権利証を処分する前に・・・・
ここで、相続の手続きの前後に登場してくる書類について、不動産の場合を例にとって、簡単に整理してみましょう。
たとえば土地の名義を持っていた父親が亡くなって、子供たちへ名義変更する手続きを行った後には、書類としては何が変わってくるのでしょうか。
まず、遺産相続をした子供たちに対しては、子供たちの名義変更された新しい権利証(登記識別情報)が発行されて、手元に届くことになります。
この権利証が、不動産の所有権に関する重要な書類であるということは言うまでもありません。
おそらく新しい権利証(登記識別情報)は大切に保管しておこう、となるでしょう。
これに対して、親の名義であった古い権利証は、遺産相続により不動産の名義が変わり、もはや権利の残っていない空の権利証となります。
今後は、子供たちの名義の新しい権利証(登記識別情報)を使うことになるわけですから、古い権利証の出番はありません。
ただし、実は、相続後に大切に保管しておくと役に立つ書類は、その親の権利証と一緒に保管されている可能性があります。
 先ほど説明した遺産分割協議書のほか、紛失すると困る書類は、先代が不動産を購入したときの資料、具体的には売買契約書や領収書などが該当します。
先ほど説明した遺産分割協議書のほか、紛失すると困る書類は、先代が不動産を購入したときの資料、具体的には売買契約書や領収書などが該当します。
古い売買契約書が大切な理由
一般に、不動産を売った場合、売却による利益や損失が出ます。
 このような不動産の譲り渡しに伴う利益や損害は、専門的な用語では不動産の「譲渡所得(じょうとしょとく)」と呼ばれます。
このような不動産の譲り渡しに伴う利益や損害は、専門的な用語では不動産の「譲渡所得(じょうとしょとく)」と呼ばれます。
つまり、譲渡しで儲(もう)けが出ている場合には、相応の税金がかけられる訳です。
 簡単に言うと、「売ったときの値段」から、「もともと買ったときの値段」などを引いた金額がこの譲渡所得となり、それがプラスとなれば、そこに税金がかかります。
簡単に言うと、「売ったときの値段」から、「もともと買ったときの値段」などを引いた金額がこの譲渡所得となり、それがプラスとなれば、そこに税金がかかります。
ですから、逆にもともとの買ったときの値段が高く、売ったときの値段が安く損している場合は、課税されることもないという仕組みです。
ただし、あいまいな自己申告では通用しません。
当然「もともと買ったときの値段」について、根拠となる書類が必要になります。この書類が、不動産を購入したときの売買契約書や領収書になります。
これらの書類の保存について特に気をつけるべきタイミングは、やはり遺産相続によって不動産の名義を取得したときでしょう。
相続の場合、不動産の名義を引き継いだ人は、亡くなった先代が購入したもともとの金額を引き継ぐことができます。売買契約書などの書類を紛失してしまうと、本来なら控除してもらえたはずの先代の購入金額は幻と消えてしまいます。
まとめ
亡くなった両親の古い権利証は必要ないといえる場合もあるかもしれません。
しかし、その古い権利証の入っていた封筒の中やその周辺に、もしかしたら他の資料が一緒になっている可能性があります。
これらの亡くなった先代の相続関係書類や不動産購入した際の契約書や資料も、後日のために大事に残しておきましょう。
 当事務所のホームページでは、もうちょっと詳しく、相続や遺言、その他の手続きについても説明しています。興味のある方は、こちらからお入りください。
当事務所のホームページでは、もうちょっと詳しく、相続や遺言、その他の手続きについても説明しています。興味のある方は、こちらからお入りください。